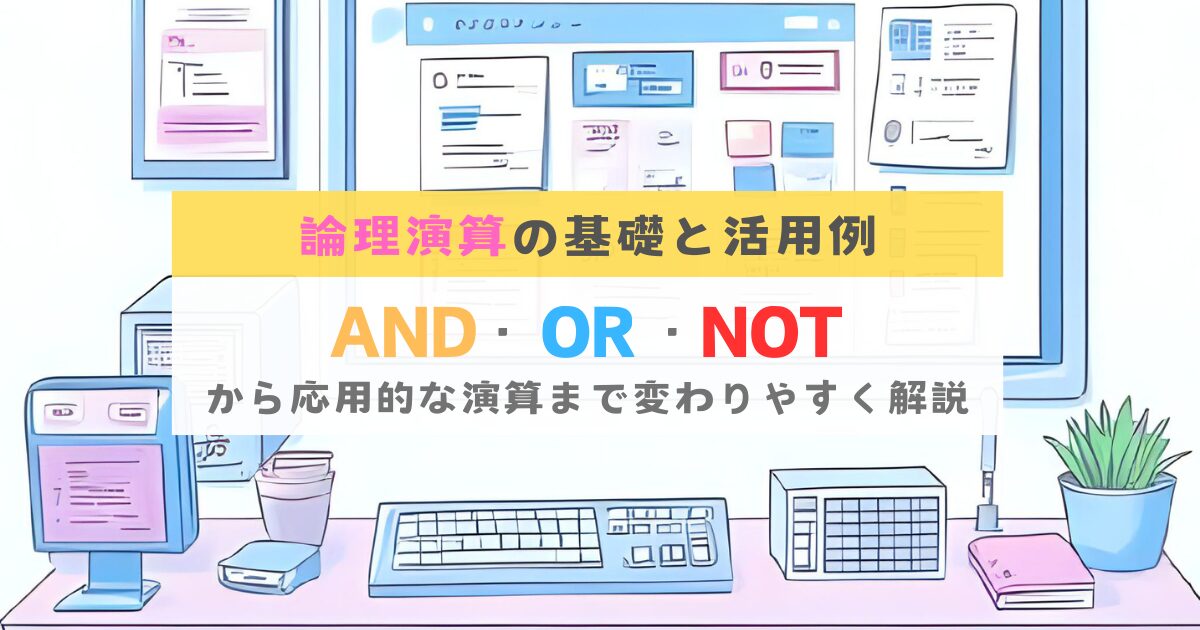私たちは毎日のように
- もし雨が降ったら傘を持っていく
- 休日か有給なら会社に行かない
といった条件判断をしています。
こうした考え方を整理したものが 論理演算 です。
論理演算とは、物事を 『真(True=正しい)』 か 『偽(False=正しくない)』 の二つに分け、その組み合わせで結論を導く仕組みのことです。
一見すると難しそうに思えるかもしれませんが、コンピュータやスマートフォンの動作から、インターネット検索、日常生活の意思決定にいたるまで、私たちの身の回りのあらゆる場面で使われています。
この記事では、論理演算の基本である AND(かつ)・OR(または)・NOT(否定) を中心に、応用的な演算や実生活での活用までをわかりやすく解説します。
TKH
読み終わる頃には「なるほど、論理演算って身近なものなんだ」と感じてもらえるはずです!
1. 論理演算とは?基本の意味と役割
論理演算の定義と「真(True)・偽(False)」の考え方
「論理演算」という言葉を聞くと、難しい数学やプログラミングを連想する人が多いかもしれません。
ですが、その本質はとてもシンプルです。
論理演算とは、『物事を真か偽かに分けて判断する仕組み』のことを指します。
ここでいう「真」と「偽」とは、次のように表すことができます。
- 真(True) = YES、正しい、1
- 偽(False) = NO、間違い、0
この二つの状態しか扱わないのが論理演算の特徴です。
一見すると単純すぎるように思えますが、
実はこの二択の組み合わせだけで、私たちの身の回りの情報処理やコンピュータの動作は成り立っています。
たとえば、次のような命題(判断できる文)を考えてみましょう。
- 「今日は雨が降っている」
- 「明日は休日である」
これらは「はい/いいえ」で答えられる内容ですよね。
例えば、「今日は雨が降っている」を先ほどの『真』 と 『偽』で表してみると、
- 雨が降っている場合 = 真(1)
- 雨が降っていない場合 = 偽(0)
といった具合に整理できます。
つまり論理演算とは、日常的な判断を形式化し、数字で扱えるようにしたルールなのです。
コンピュータと人間の思考における論理演算の役割
上記のような論理演算は、人間の思考とコンピュータの処理の両方に深く関わっています。
人間の思考における論理演算
私たちは日常のあらゆる場面で「もし〜なら」「〜でなければ」といった論理を無意識に使っています。
- 「もし雨なら傘を持っていく」
- 「もし仕事が終わればテレビを見る」
- 「休日または有給なら会社に行かない」
これらはすべて論理演算の形に置き換えられます。
つまり論理演算は、人間が考えやすい『条件判断の型』を表しているのです。
コンピュータにおける論理演算
一方で、コンピュータは 0と1(二進数) しか理解できません。
0と1かというのは、スイッチがオン(1)かオフ(0)(→電流が流れている(1)か流れていない(0))か、という二値の世界です。
そのためコンピュータは、複雑な処理をすべて「論理演算」に分解して動いています。
具体的な処理内容の説明は割愛しますが、
私たちが「ボタンをクリックする」といった操作も、裏側では論理演算の組み合わせとして処理されているのです。
ここまでのまとめ
ここまでの内容を一旦整理すると、論理演算は、
- 人間にとっては「考えを整理する道具」
- コンピュータにとっては「動作を決める最小単位」
という役割を果たしています。
以上から論理演算は、人間の論理的思考とコンピュータの情報処理をつなぐ共通言語と言えるかもしれません。
2. 論理演算の基本3種類(AND・OR・NOT)
ここまでで、論理演算の基礎となる『物事を真(True=1)か偽(False=0)に整理して判断する』という考え方を学びました。
ここからは、その真(True=1)か偽(False=0)を使ってより複雑な条件判断をしていきます。
まずは、基礎となる 3種類の基本演算子(AND・OR・NOT) を見ていきましょう。
この3つを理解すれば、論理演算の考え方の大部分が身につきます。
AND(かつ)の定義と例
AND(かつ)は『両方の条件が真のときにだけ真になる』という演算です。
以上の定義を踏まえて、『外出する条件』を例に見てみましょう。
例:外出する条件
- 条件① : 今日は日曜日
- 条件② : 天気が晴れ
この場合、『今日が日曜日で かつ(AND) 晴れている』なら外出します。
どちらか一方でも欠ければ外出しません。表で表すと以下のようになります。
| 日曜日か? | 晴れているか? | 外出するか? |
|---|---|---|
| 真 | 真 | 真(外出する) |
| 真 | 偽 | 偽(外出しない) |
| 偽 | 真 | 偽(外出しない) |
| 偽 | 偽 | 偽(外出しない) |
OR(または)の定義と例
OR(または)は『どちらか片方でも真であれば真になる』という演算です。
以上の定義を踏まえて、『飲み物を用意する場合』を例に見てみましょう。
例:飲み物を用意する場合
- 飲み物があると判断する条件① : お茶がある
- 飲み物があると判断する条件② : コーヒーがある
この場合、『お茶がある または(OR) コーヒーがある』なら飲み物があると判断して、飲み物を用意します。
どちらも無ければ飲み物は用意できません。表で表すと以下のようになります。
| お茶があるか? | コーヒーがあるか? | 飲み物を用意できるか? |
|---|---|---|
| 真 | 真 | 真(飲み物あり) |
| 真 | 偽 | 真(飲み物あり) |
| 偽 | 真 | 真(飲み物あり) |
| 偽 | 偽 | 偽(飲み物なし) |
NOT(否定)の定義と例
NOT(否定)は『真を偽に、偽を真に変える』という演算です。
以上の定義を踏まえて、『電気のスイッチ』を例に見てみましょう。
例:電気のスイッチ
- 条件 : 電気がついている
表で表すと以下のようになります。
| 電気がついているか? | NOT適用 | 結果 |
|---|---|---|
| 真(ついている) | 偽 | 電気はついていない |
| 偽(ついていない) | 真 | 電気はついている |
ここまでのまとめ
AND・OR・NOTを、それぞれ一言で整理すると以下のようになります。
- AND(かつ):両方が真のときだけ成立
- OR(または):どちらか一方でも真なら成立
- NOT(否定):真偽を逆にする
この3つは、論理演算の基本の中でも最も重要なルールです。
次に学ぶ XOR・NAND・NOR といった応用的な演算子も、この3種類を理解していればスムーズに理解できます!
3. 応用的な論理演算子
ここまでで、論理演算の基本である AND・OR・NOT を学びました。
これらは論理演算の「三本柱」であり、すべての複雑な条件式の基礎になります。
次は、ここから一歩進んで、より応用的な演算子である
- XOR(排他的論理和)
- NAND(否定論理積)
- NOR(否定論理和)
を見ていきましょう。
TKH
これらを理解すると、電子回路やプログラミングでの活用の理解がより深まります!
XOR(排他的論理和)の定義と例
XOR(排他的論理和)は『どちらか一方が真のときに真になる』演算です。
以上の定義を踏まえて、『電気のスイッチ』を例に見てみましょう。
例:電気のスイッチ
部屋の電気のスイッチが2つ(スイッチ1, スイッチ2)あります。
それぞれ、1回押すと点灯、2回押すと消灯という動作になる、ごくごく一般的なスイッチです。
この場合、
- 片方だけ押す → ランプが点灯(真)
- 両方押す(または両方押さない) → ランプは消灯(偽)
という感じになりますね。
このイメージがXOR(排他的論理和)になります。
表で表すと以下のような感じです。
| スイッチ1 | スイッチ2 | 電気はついているか |
|---|---|---|
| 真(押す) | 真(押す) | 偽 |
| 真(押す) | 偽(押さない) | 真 |
| 偽(押さない) | 真(押す) | 真 |
| 偽(押さない) | 偽(押さない) | 偽 |
TKH
全くボタンを押さないと、もちろん電気はつきません。
2つのスイッチを押すと、点灯→消灯となり、電気は消えてしまいます。そんなイメージです!
NAND(否定論理積)の定義と例
NAND(否定論理積)は『ANDの否定(NOT)』です。
つまり、『両方が真であるときだけ偽』になり、それ以外は真になります。
以上の定義を踏まえて、『安全装置』を例に見てみましょう。
例:安全装置
スイッチが2つ(スイッチA, スイッチB)ついている『危ない機械』があります。
この『危ない機械』は、スイッチAとスイッチBを同時に押してしまうと、大変危険な動作をします。
そんな時、NANDの機構を持った安全装置を使って『危ない機械』を制御することで、
両方のスイッチがオンの時は強制的に『危ない機械』の電源をオフにし、安全な稼働が実現できます。
| スイッチ1 | スイッチ2 | 危ない機械の電源 |
|---|---|---|
| 真(オン) | 真(オン) | 偽(オフ) |
| 真(オン) | 偽(オフ) | 真(オン) |
| 偽(オフ) | 真(オン) | 真(オン) |
| 偽(オフ) | 偽(オフ) | 真(オン) |
NOR(否定論理和)の定義と例
NORは『ORの否定』です。
つまり『両方が偽のときだけ真』になります。それ以外は偽になります。
以上の定義を踏まえて、『部屋が静かな状態であるか』を例に見てみましょう。
例:部屋が静かな状態であるか
- 条件① : 窓が開いている
- 条件② : 掃除機をかけている
窓が開いていたり、掃除機をかけていると部屋は静かではありませんよね。
静かな状態になるには、窓を閉めて、掃除機をかけるのはやめる必要があります。
表に表すと以下のようになります。
| 窓が開いている | 掃除機をかけている | 部屋が静かである |
|---|---|---|
| 真(開) | 真(かけている) | 偽 |
| 真(開) | 偽(かけていない) | 偽 |
| 偽(閉) | 真(かけている) | 偽 |
| 偽(閉) | 偽(かけていない) | 真 |
ここまでのまとめ
XOR・NAND・NORを、それぞれ一言で整理すると以下のようになります。
- XOR :どちらか一方が真のときだけ真(→両方真は偽)
- NAND :両方真のときだけ偽。ANDの否定
- NOR :両方偽のときだけ真。ORの否定
これら応用的な演算子は、一見ややこしく感じるかもしれませんが、真理値表を見ればルールは明快です。
TKH
次の章では、論理演算子が日常でどのように使われているのか見ていきましょう!
4. 論理演算の身近な使い方と実例
前章では、AND・OR・NOT などの基本演算子と、XOR・NAND・NOR といった応用演算子を解説しました。
「数式や真理値表はわかったけど、実際にどんな場面で使えるの?」と感じる方もいるかもしれません。
実は論理演算は、検索エンジンやアプリ、データベース、さらには日常のちょっとした判断にまで広く応用されています。
ここでは具体的なシーンを通して、論理演算がどれほど身近な存在かを見ていきましょう。
検索エンジンでの論理演算
インターネット検索では、論理演算の考え方がそのまま活用されています。
Google などの検索エンジンは、キーワードを組み合わせることで検索結果を絞り込んだり広げたりします。
例えば……
キーワード例:「株 AND 投資」
→ 「株」と「投資」の両方を含む記事がヒットします。
→ この例だと、投資信託や株式投資に関する記事を効率よく見つけられます。
TKH
ANDは、検索エンジンでデフォルトで使用される演算です。
複数のキーワードを入力して普通に検索すると、このAND演算が行われます!
キーワード例:「株 OR FX」
→ 「株」または「FX」を含む記事がヒットします。
→ この例だと、投資ジャンルを広く調べられます。
TKH
実際に、「株 OR FX」のように検索窓に入力することでOR検索ができます!
キーワード例:「投資 NOT 仮想通貨」
→ 「投資」を含むけれど「仮想通貨」を含む記事は除外します。
→ この例だと、株や投資信託を調べたいけど、仮想通貨は興味がない場合などに使えます。
TKH
NOTをGoogle検索で使うときは「-」を使います。
「投資 -仮想通貨」のように入力すると、キーワード「仮想通貨」を除外して検索できますよ!
日常生活に潜む論理演算
前の章の具体例で少し出てきましたが、実は私たちは無意識に論理演算を使って行動を決めています。
例①:ランニングする
- 条件① : 体調が良い
- 条件② : 雨が降っていない
この場合、『体調がいい かつ(AND) 雨が降っていない』ならランニングします。
どちらか一方でも欠ければランニングはしませんね。
例②:映画を見に行く
- 条件① : 友達の予定が空いている
- 条件② : 映画館の席が空いている
この場合、『友人の予定が空いている かつ(AND) 映画館の席が空いている』なら映画を見に行きます。
例①:会社を休む
- 条件① : 休日である
- 条件② : 有給である
この場合、『休日である または(OR) 有給である』なら会社は休みます。
例②:友人に連絡を取る
- 条件① : 電話がある
- 条件② : パソコンがある
この場合、『電話がある または(OR) パソコンがある』なら友人へ連絡を取ることができます。
例①:友人と食事に行く
- 条件 : 残業がある
この場合、『残業 ではない(NOT)』なら、友人と食事に行きます。
例②:外出する
- 条件 : 天候が悪い
この場合、『天候が悪い ではない(NOT)』なら、外出します。
こうして考えると、論理演算は人間の意思決定の型でもあることが分かります。
TKH
実際は、もっとたくさんの条件が複雑に絡み合っていますけどね!
プログラミングやデータベースでの使い方
今度は少し高度な使い方になりますが、プログラミングやデータベース操作でどのように利用されるかを見ていきます。
プログラミングやデータベースを操作するうえで、論理演算は必要不可欠です。
特に、現ITエンジニアの方や、将来ITエンジニアをを目指している方は絶対に避けて通れない道なので、必ず抑えておきましょう。
プログラミングでの使い方
アプリやゲームなどのプログラミングの動作条件は、論理演算の組み合わせで制御されています。
RPGゲームで具体例を見てみましょう。
例:戦闘を続ける条件
- 条件① : 味方のHPが1以上である
- 条件② : 敵のHPが1以上である
この時、『条件① AND 条件②』の場合、戦闘を続けます。
プログラム(Python)で書いてみると以下のような感じです。
# プレイヤーと敵のHP
player_hp = 50
enemy_hp = 30
# AND条件:両方のHPが0より大きいとき戦闘を続ける
if player_hp > 0 and enemy_hp > 0:
print("戦闘を続ける")
else:
print("戦闘終了")例:ドアを開けられる条件
- 条件① : 「鍵」アイテムを持っている
- 条件② : コインを100枚以上持っている
この時、『条件① OR 条件②』の場合、ドアを開けます。
プログラム(Python)で書いてみると以下のような感じです。
# 所持状況
has_key_item = False
coins = 120
# OR条件:アイテムを持っている、またはコインが100枚以上ならドアを開けられる
if has_key_item or coins >= 100:
print("ドアを開けられる")
else:
print("ドアを開けられない")データベースでの使い方
データベースは主にSQLと呼ばれる言語で操作されますが、そのSQLでも論理演算が利用されます。
具体例は以下のような感じです。
例:usersテーブルから特定のユーザーを抽出する場合
- 条件① : 年齢が20歳以上である
- 条件② : 女性である
この時、『条件① AND(かつ) 条件②』のユーザーを抽出したい場合、以下のようなSQL文になります。
-- WHERE句で抽出するユーザーを指定する
SELECT *
FROM users
WHERE age >= 20
AND gender = 'female';例:productsテーブルから特定の商品を抽出する場合
- 条件① : 価格が1000円以上である
- 条件② : 在庫数が10個以上である
この時、『条件① OR(または) 条件②』の商品を抽出したい場合、以下のようなSQL文になります。
-- WHERE句で抽出するユーザーを指定する
SELECT *
FROM products
WHERE price >= 1000
OR stock >= 10;プログラミング・データベースでの使い方まとめ
難しく感じる方もいたかもしれませんが、プログラミングでもデータベースでも、やっていることは結局「条件を満たすかどうか」を判断しているだけです。
繰り返しになりますが、現ITエンジニアの方や、将来ITエンジニアを目指している方にとっては必須の知識なので、必ず抑えておきましょう。
6. さいごに
論理演算は、数式やプログラミングなどの専門知識だけではなく、私たちの生活を支える考え方のひとつということがわかっていただけたかと思います。
- AND(かつ)は「両方そろったときに成立」
- OR(または)は「どちらか一方でOK」
- NOT(否定)は「真偽をひっくり返す」
このシンプルなルールが組み合わさることで、コンピュータの複雑な処理も、検索エンジンの仕組みも、日常の小さな判断も成り立っています。
論理演算を知っていると、プログラムを書くときもデータを扱うときもスッキリ理解できるようになりますし、普段の考え方を整理するのにも役立ちます。
身の回りや自分の思考を観察してみてみると、「あ、ここでも論理演算が使われている!」という新しい発見があるかもしれません!
以上、簡単でしたが論理演算についての解説でした。
それでは皆さん、良いITライフを!